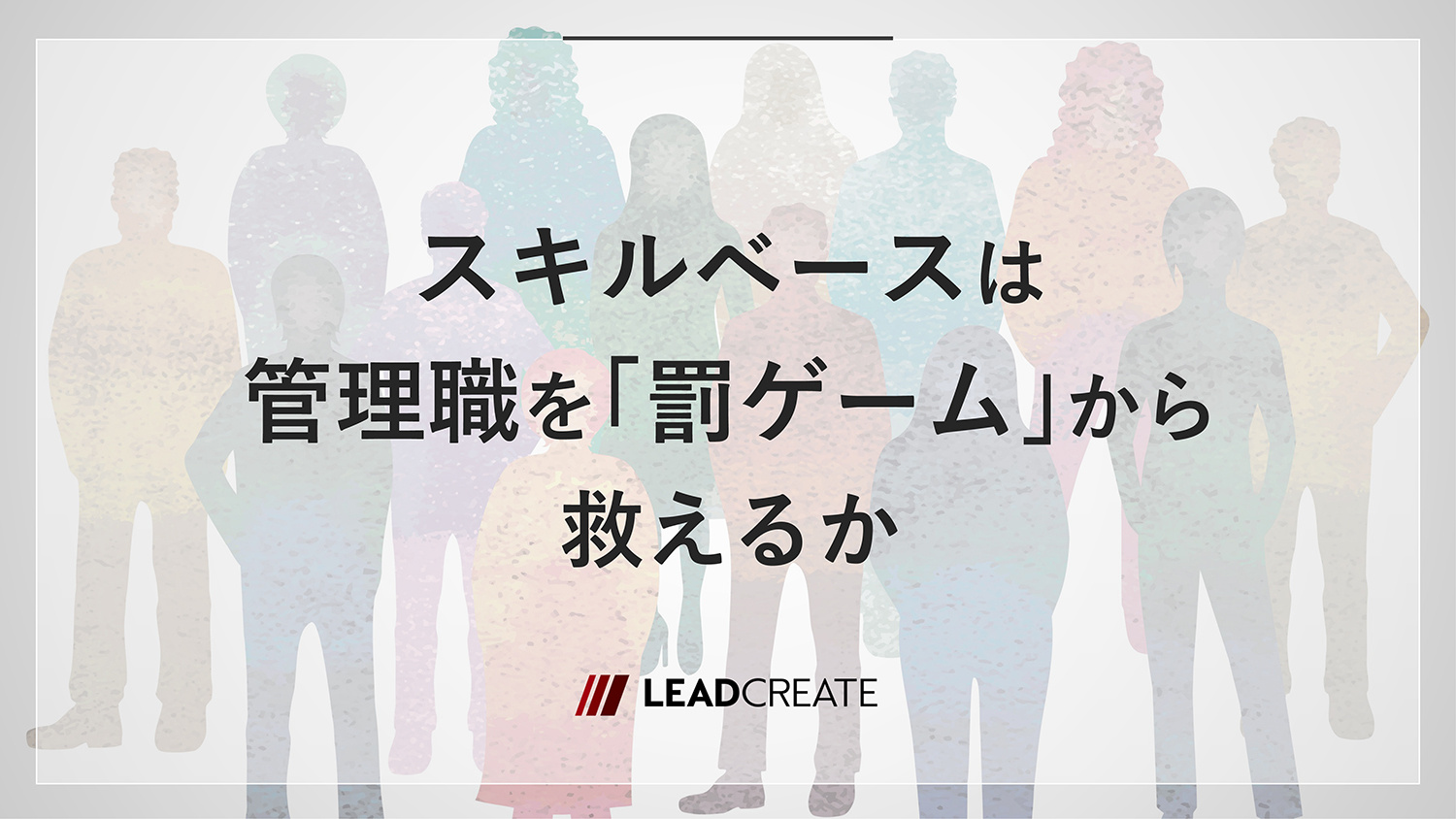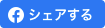2024年以降、「スキルベース」という人材マネジメントの考え方が話題に上がっており、私もIT業界を中心に複数の企業でその導入や可能性について議論をしています。
本コラムでは、改めて「スキルベース」の概念を解説するとともに、日本では社会問題になっている「管理職の罰ゲーム化」に対する処方箋としての可能性を考察してみたいと思います。
この記事の著者

株式会社リードクリエイト
ソリューション事業本部 マーケティング推進室
並川 喜則
2008年8月よりリードクリエイトに参画。人事評価や360度、アセスメントプログラムの導入や運用支援を中心に、各社の人事課題解決に取り組む。近年は企画や設計だけでなく、社内での説明会や勉強会を行うなど、より人事の現場に踏み込んだ活動をしている。
スキルベース型人材マネジメントについて
「スキルベース」の人材マネジメントのイメージは、「メンバーシップ型」と「ジョブ型」と比較してみると想像しやすいと思います。
「メンバーシップ型」
メンバーシップ型は、日本でいう職能資格制度を軸にした人材マネジメントのことで、保有する職務能力レベルによって資格・グレードを定めることです。職務能力は経験を積むことで伸長するため、能力が上がれば次の資格・グレードに進めます。人に仕事をつけ、人事管理は会社(人事管理部門)がする等を主な要素にしています。前提は終身雇用やそれに準じる長期雇用で、若い時から頑張れば、一つずつ着実に、そして順番に、資格や職位が上がる仕組みです。ある調査では日本企業の8割ほどは「メンバーシップ型」という結果が出ています。決して仕組みそのものが悪いわけではありませんが、世の中の変化に合わせて進化してこなかったことが原因で、多くの問題が浮き彫りになっています。
「ジョブ型」
ジョブ型は、日本ではさまざまな運用がされていますが、元々は役割や仕事・職務の内容や報酬を定義(職務定義書/JD)して、それを資格・グレードに割り当て、その職務に適した人をあてるという人材マネジメントの考え方です。
日本ではコロナ禍を機に急速に普及しましたが、考え方自体は職務等級制度が昔からあります。近年日本企業で導入される「ジョブ型」の多くは役割等級制度というもので、ジョブ(職務)それぞれを定義して運用するものではなく、設定したグレードに相当する役割でジョブを括る形が多いです。例えば、あるグレードは「課に該当する組織のマネジャーとして成果責任と人材育成責任を果たす」という役割を担うジョブを括って運用しています。職務等級制度ほど厳密な運用を行わない、ある意味で日本的なジョブ型マネジメントと言えます。もちろん、一つひとつのジョブを定義して運用する会社もあり、どちらが良い悪いというものではありません。各社の人事・人材育成のコンセプト、ポリシーによって異なると言えます。
両者の大きな違いは、人に仕事をつけるか、仕事に人をつけるかです。ジョブ型は、まず仕事や役割を前提に、組織サイズやポスト・ジョブの数が決まっている中で、人をアサインしていくことになります。従って、未だ多くの日本企業が行っている新卒一括採用との相性は良いとは言えず、苦肉の策として、入社から管理職手前まではメンバーシップ型で、成長が認められれば次の資格・グレードに上がり、管理職以上はポスト・役割数を管理し、空いたポストにアサインするといった、ハイブリッド型運用をしている会社もあります。
「スキルベース型」
スキルベース型という考え方を一言でいえば「その仕事に必要な能力を持っている人(達)がやる」でしょうか。これはユニリーバ社など海外の人材マネジメントに先進的な取り組みをしている会社によって始められました。
その背景にあるのは「ジョブ型人材マネジメント」の制度疲労です。この制度疲労は「設定したジョブの妥当性がなくなってきた」というものです。以前からジョブ型の問題点として、組織がサイロ化することや、ジョブとジョブの隙間の仕事などが挙げられていました。そして近年はジョブに定義されたこと以外の業務に携わるメンバーが増えたり、AIの登場を含むDXによって業務内容が変わり続けたりしています。
加えてコロナ禍を起点に働き方の多様化がまた一段と進んだことも原因と考えられます。正規雇用にこだわらず、業務委託・フリーランスなどの形式で業務に携わる人材や、それを希望する人材が増えてきたとも言われます。
そこで考えられたのが、従来のジョブに含まれていた職務やプロジェクト、さらにはタスクを、スキルという単位で分解し、スキルごとにアサインしていこうという試みです。
「Aという仕事に必要なスキルが①②③」だった場合、ジョブ型マネジメントの考え方では、①②③を満たす人材○○さんをAという仕事にアサインします。スキルベース型マネジメントの考え方では、①②を△△さんに、③を□□さんにアサインしてAという仕事を2人で遂行してもらいます。また△△さんに④というスキルがあれば、Bという仕事を兼務することも可能です。
このメリットは、より人材の強みにフォーカスしたアサインができること、組織やジョブ、プロジェクトにより柔軟性や迅速性を持たせられることにあります。スキルベースというよりスキルマッチングと言い換えたほうがイメージしやすいかもしれません。
この取り組みを支えているのはDXです。ジョブに必要なスキルとそのレベルを網羅したデータと、人材のスキル保有レベルをマッチングしたり判定したりするためのプラットフォームやAIが必要(社内人材マーケットプレイス)です。DXによって改革を余儀なくされた人材マネジメントを、DXが下支えしているから実現できているというのは皮肉とも感じます。
「管理職の罰ゲーム化」が進む背景と理由
さて、ここまで「メンバーシップ型」「ジョブ型」「スキルベース型」の人材マネジメントについて説明してきましたが、少しテーマを変えて「管理職の罰ゲーム化」について触れていきます。
以前から管理職になりたくないという若手・中堅社員が増えているとの声はありましたが、最近はまさに社会問題にまでなってきたと言えます。この問題に対して、私たちリードクリエイトは、大きく2つの原因があると考えています。1つ目は「管理職の多重債務化」、2つ目は「管理職の準備と見極めの不足」です。
管理職の多重債務化
1つ目の「管理職の多重債務化」について、いくつか理由が考えられます。まずは「挑戦や変革」といった攻めと「コンプライアンスや労務管理」といった守りのようなさまざまなダブルバインドの存在です。長期成果を求めながら短期成果にこだわるのも同様です。そして働き方改革の表面的な取り組みとして、労働時間の削減も理由の一つです。メンバーの労働時間を削減したことで残った業務は、管理職が巻き取っているケースが多く見られます。そしてそれら業務の遂行責任と成果責任を果たしつつ、チームづくりやメンバーの育成もしなくてはいけません。結果、管理職は多重債務者に陥っていきます。
管理職の準備と見極めの不足
2つ目の「管理職の準備と見極めの不足」については、人事に携わる方でなくても、業務のことを何もしらない新入社員が、一人前として成果を出すためには数年かかることは理解できるはずです。本来であれば管理職、マネジメント業務も同じように捉えることが望ましいのですが、管理職前の準備がないままに役割を付与することが多く見受けられます。全員にはできないということであれば、ある程度候補者を絞っても、準備をさせるべきではないでしょうか。そしてこの準備ができているかどうかを見極めず、準備ができていないにもかかわらず、1つ目のような環境に送り込むため、より「管理職の罰ゲーム化」が進んでしまうのだと思います。
「管理職の罰ゲーム化」とスキルベース型人材マネジメント
そして、この「管理職の罰ゲーム化」を解消するために有効だと考えられるのが、管理職の分業です。日本の大手企業の中にも、すでに取り組みを始めているところがあります。私たちリードクリエイトも管理職の分業化を推奨しており、特に事業推進と組織活性・人材育成を分業することで、管理職という役割の負荷を軽減するだけでなく、適性を見極めてアサインすることが容易になるのではないかと考えています。
今回紹介した「スキルベース型人材マネジメント」は、前述の通りジョブや階層に関係なく、役割遂行に必要なスキルを定義し、そのスキルを保有する人材をアサインすることで、組織運営を行う考え方です。これを全社的に運用することは非常にハードルが高くなりますが、管理職の役割分業に特化して運用すれば、ハードルは大きく下がります。ピープルマネジメントに求められるスキルは、大きく変わることはないでしょうし、タスクマネジメントはジョブ型を志向した企業であればある程度スキルの整理ができていると考えられます。
また、これまで職能資格制度を運用してきた会社についてくる、部下なし管理職(担当課長・担当部長など)が増えている問題も、タスクマネジメントを任せる管理職とすることで一定以上解消することができるのではないでしょうか。職能資格制度や役割等級制度を導入し、いわゆる複線型の管理職コースを設けている会社においては、第3の管理職として、運用に柔軟性をもたらすことにも繋がります。
従業員側にとっても、何でもやらないといけないライン管理職か、高度専門職たるスペシャリストのどちらかではなく、そこに第3の選択肢が加わることで、より自身のキャリアを選びやすくなるのではないかと思います。
まとめ
「スキルベース型人材マネジメント」は、まだまだ日本企業での運用実績が乏しく、導入のポイントやメリット・デメリットが実践知として体系化されていません。ただ上記の通り、その考え方に則って、分業化を実現するための手段として活用し、「管理職の罰ゲーム化」を軽減していくことには、十分な価値と可能性があると考えます。
リードクリエイトでは、各社の現状や事業・組織ビジョン、人的資本基本方針などに基づいて、最適な人事制度や制度運用の仕組みをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。
LEADCREATE NEWS LETTER
人事・人材開発部門の皆さまに、リーダー育成や組織開発に関するセミナー開催情報や事例など、実務のお役に立てるような情報を定期的にお届けします