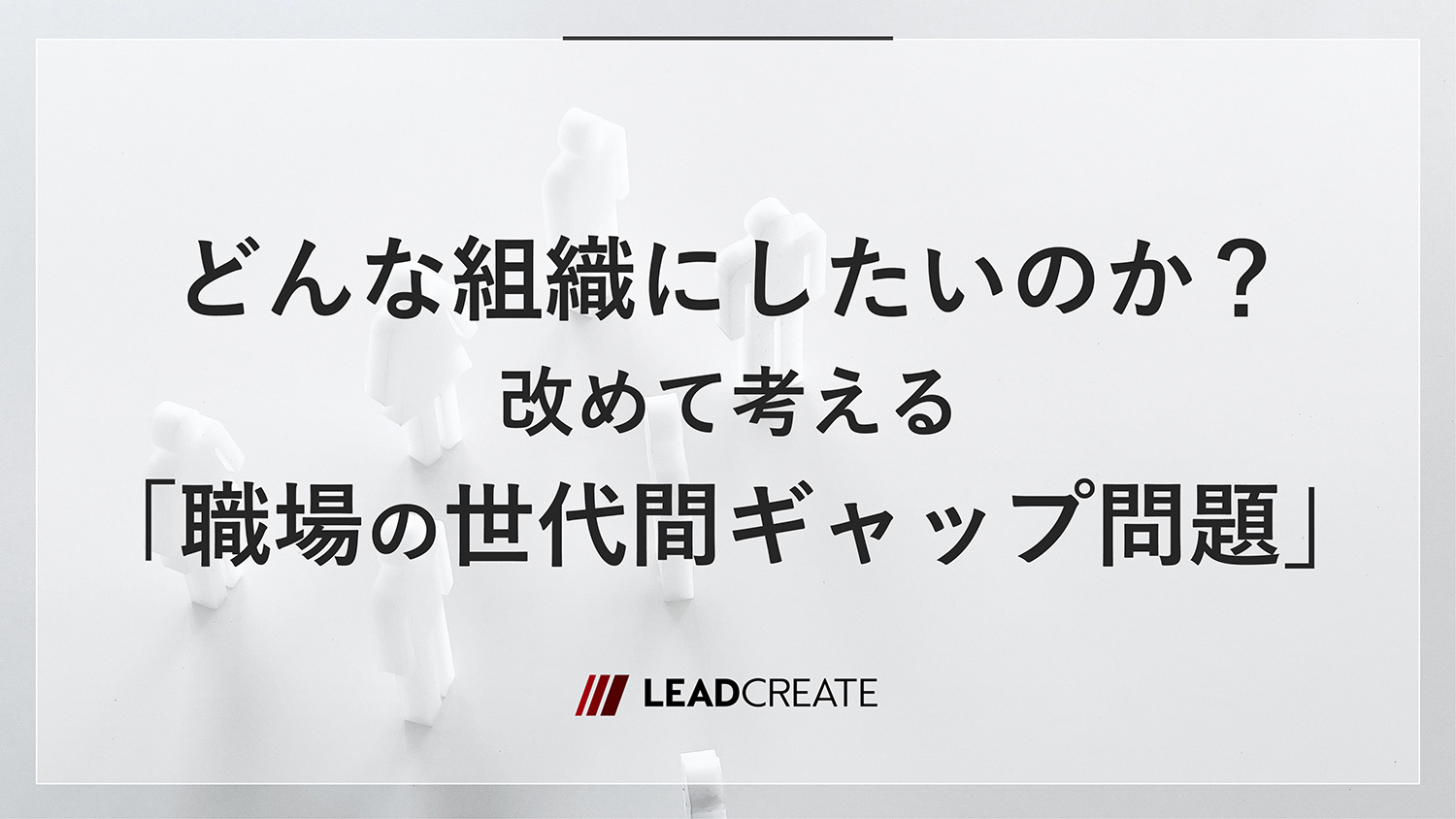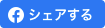近年の人材流動化の促進に伴い、多くの企業において若手社員の定着に関するお悩みを多く聞きますが、その際の論点の一つとして、世代間コミュニケーションが挙げられます。
異なるバックグラウンドや価値観を持つ多様な世代が共存する職場においては、従来の関わり方やスタイルでは効果的に機能しないことが増えています。世代間のギャップが生む衝突や誤解は、組織のパフォーマンスに深刻な影響を及ぼす可能性があります。
このギャップの解消に向けては何が重要でしょうか?また、どのようなコミュニケーションが世代を超えた理解を深めることができるのでしょうか?このコラムを通じて、その解決のヒントを探っていきたいと思います。
この記事の著者

株式会社リードクリエイト
ソリューション事業本部 ソリューションパートナー室 兼 マーケティング推進室
辛 鐘世
2005年よりリードクリエイトに参画。アセスメントプログラムや階層別教育施策の導入運用を中心に、各社の組織課題や人事課題の解決の支援に携わる。近年はこれまでの経験や支援で培った知見をマーケティング施策にも展開し、多くの企業の課題解決に寄与する情報を設計・発信中。
世代間のコミュニケーションギャップとはなにか
世代間のコミュニケーションギャップは今に始まったことではなく、いつの時代においても起きていることですが、その要因は様々です。
例えば、デジタルネイティブ世代と呼ばれる若者たちは、情報収集やコミュニケーションの手段が過去とは根本的に異なるため、これが職場での理解を妨げる一因になっています。また、経済状況の変化も重要です。バブル経済を背景に育った世代と、リーマンショック以降の厳しい雇用環境で成長した世代では、職業観や収入に対する価値観も異なることがあります。さらには、家庭環境や教育の違いも無視できない要素です。このように、一つの組織においても多様な価値観を持つ世代が共存するため、時には対立や誤解を生む要因になります。
参考までに、現在の職場には一般的に5つの世代が存在していると言われます。『ベビーブーム世代』は、勤勉さや忠誠心を重んじ長期雇用を重視しています。『団塊ジュニア世代』は、仕事とプライベートのバランスを求める傾向が強く、ライフスタイルの多様化が見られます。『氷河期世代』は、採用難の経験があるため真面目で組織方針に従順な面があります。『ミレニアル世代』は、技術に親しみがあり自己表現や社会的責任にも敏感な世代です。『Z世代』は、デジタルネイティブであり、迅速な情報共有や変化を求める姿勢が特徴です。また、これらの世代間では働くモチベーションや価値観が異なるため、組織やメンバーとの関係性やコミュニケーションスタイルにも多様性が生まれます。
近年、世代間ギャップの可視化に向けた研究が多くなされています。例えばある調査によると、若年層においては仕事に対する期待や価値観が多様化しており、「安定した仕事」よりも「自己成長やワークライフバランス」を重視する傾向が強いことが見えています。また、職場におけるコミュニケーションの充実度や満足度にも違いが見られ、特にミレニアル世代やZ世代は、SNSを通じた迅速な情報共有を求める傾向があります。これに対し、中高年齢層の世代では、対面でのコミュニケーションや丁寧なやり取りを重視する傾向があります。このような傾向は、世代間の相互理解を深めるための重要な情報となります。こうした情報を活用して世代間のコミュニケーション改善に取り組んでいくことが必要と言えるでしょう。
コミュニケーションのベースを築くための土壌
人事担当者との意見交換において、世代間ギャップを解消していくための主体をリーダーや役職者に設定することが多くあります。この視点が間違っているわけではありませんが、それではリーダーや役職者の疲弊に繋がり、管理職になりたがらない若手社員の増加を招く一因にもなり得ます。円滑なコミュニケーションの実現主体は双方にあります。リーダーや役職者が若手や一般社員に合わせるということではなく、双方がギャップを埋めていくために行動を変えていく必要があります。
上記を踏まえ、前述したような各世代の文化的背景(育った環境や教育、社会的経験など)を理解することが非常に重要です。例えば、ベビーブーム世代は戦後の復興や高度経済成長を体験し、安定した生活を重視する傾向が強いと言われますが、ミレニアル世代やZ世代は、グローバル化や情報化社会の進展もあり、より自由で多様な価値観を持つようになっています。また、デジタル機器の発展によって育った若い世代は、情報の即時性やアクセシビリティを重視し、コミュニケーションの手段も多様化しています。このような文化的背景を理解することで、相手の意見や考えを尊重したコミュニケーションスタイルを適応することが可能になります。この理解を深めることが、世代間の信頼関係を築く基盤となります。
オープンな対話も不可欠です。オープンな対話に向けては何が必要か?それは自らの考えや価値観を押しつけるのではなく、関係者の意見や感情を尊重し、積極的に耳を傾ける姿勢が重要です。それにより相手は安心感を持ち、自由に意見を表明しやすくなります。また、このような環境は世代を超えた相互理解を育むだけでなく、新しいアイデアや解決策が生まれる土壌を提供します。失敗を恐れずに意見交換できる文化は、組織全体のイノベーションを促進する要因ともなり得ます。
時勢に合った職場環境の整備も不可欠です。多くの企業で導入され始めていますが、オープンなスペースやフレキシブルな作業場所へとシフトすることが、世代を超えた対話を生む一助となります。職場にリラックスできるスペースや交流エリアを取り入れることで、世代を超えた社員同士の自然なコミュニケーションが生まれやすくなります。さらに、フレックスタイムやリモートワークの導入も、各世代のライフスタイルに応じた働き方を提供することになります。職場環境の見直しを行うことで、世代間の理解を深め、より協働的な文化を形成することができるでしょう。
【事例】異なる価値観を活かすための工夫
具体的な取り組みとしてはどのようなことを行っているのか、他社事例をご紹介します。
事例1|メンター制度の導入
シニア世代をメンター、若手社員をメンティーとしたメンター制度は、異なる世代間のコミュニケーションを促進し、価値観の理解を深めるうえで効果的な手段です。
若手社員は職場で直面する課題に対してメンターより助言や指導を受け、具体的な問題解決を実現します。メンターにとっても新しい視点や知見を得る機会となり、やりがいにつながる効果が見込めます。また、副次的には技能伝承の観点において、経験豊富なシニア世代の知識やスキルを次世代に伝えることもできます。
メンター制度をうまく機能させるためには、トレーニングやサポート体制を充実させることが必要なため、組織としての仕組みや綿密な準備が求められますが、世代間の壁を越えた対話が生まれ、組織内でのコミュニケーションが豊かになることが期待されます。
事例2|多世代メンバーをチームとしたプロジェクト活動
社内プロジェクト等において、メンバー構成を多世代化することで異なる経験や考え方が交わり、新しいアイデアや解決策が生まれる土壌が形成されます。
各世代のメンバーがオープンなコミュニケーションを促進することで、チームメンバー同士が相互に学び合い、成長できる場が生まれます。プロジェクト推進のプロセスにおいては、共通の目標設定と役割分担が重要なポイントになります。各メンバーが自分の強みを活かし役割を果たすことで、チーム全体のパフォーマンスが向上し、各メンバーの信頼関係や認め合う意識が高まります。
これらの取り組みを通じて、世代間の違いや価値観を乗り越え、組織の競争力を高めていくことができます。
事例3|リーダーシップスタイルの見直し
トップダウン型のアプローチは、特に若い社員にとっては受け入れられにくい場合があります。そのため、特にリーダーは相互尊重をベースとしてコミュニケーションを促進するスタイルへシフトすることが必要です。
具体的には、フィードバック制度の導入や意見を言いやすい風土醸成が肝です。リーダーは、メンバーの意見やアイデアを積極的に取り入れ、決定プロセスに参加させることで、自身の価値を感じさせることができます。また、リーダー自身が自己開示を行い、自分の経験や失敗談を共有することも、チームの信頼感を高める手助けになります。
このようにリーダーシップスタイルを見直すことによって、世代間の対立を減らし、共通の目標に向かって協力し合う組織文化を醸成することができます。
これからの組織変革の可能性
ある企業では、さまざまな世代の社員が定期的に集まる場を導入しました。具体的には、月に一度の「交流会」を開催し、各世代から参加者を集い、主催者サイドで設定したテーマに沿ったディスカッションを行います。ディスカッション内容は基本的に制限はありませんが、「他者意見の尊重」という一つのルールだけは守ることを前提としています。
この取り組みにより、各社員は自分の意見を表現する機会を得ると同時に、他世代の考え方や思いを知ったり、新しい視点を取り入れたりすることができ、双方の相互理解が進む効果が見られました。その結果、職場の雰囲気が大いに改善され、仕事の効率も向上されたとともに、社員同士の信頼関係がさらに磨かれていったようです。
一方、ある企業では若手社員が提案した新しいアイデアをシニア社員が軽視し、結果として革新的な改善策が実現しなかったケースがあります。その要因を探ると、シニア社員が持つ「過去の成功体験」に固執し、若手社員の新しい視点を受け入れられなかったことがありました。
この事例は、異なる世代の意見を尊重しないことで、イノベーションのチャンスを逃す危険性を示します。他方、若手社員もシニア社員が受け入れてくれないことに納得がいかず、横柄な態度を取ってしまったことも反省すべき点でした。この事例から言えることは、どちらか一方だけの責任に目を向けるのではなく、双方の変化を目指し、その意識や行動を変えていく必要性と言えます。
少し視点を変え、今後も今までの価値観に沿った組織運営で良いのか?という問いを立てて見ることも必要と考えます。上司と部下、ベテランと若手といった階層や年齢で区分けされた組織が一般的ですが、そもそもの組織のあり方や考え方を変えていく必要もあるのではないでしょうか。組織というコミュニティをどう捉えるのか、どんな組織にしていきたいのか、その問いを改めて検討していくことも必要な時期に来ているのかもしれません。組織のありたい姿を現状の延長線上において、ギャップの解消を考えていくのか、そもそものあり方から再検討していくのか、その設定によってはアプローチも大きく変わっていくことになります。人事部門として、現状是正から脱却し、新たな組織づくりの観点へと変化を遂げていくことも必要と考えます。
最後に
世代間のコミュニケーションギャップは、多かれ少なかれどの組織においても起きている現象と言えますが、適切なアプローチを取ることで大きな強みに変えることができます。そのために、まずは一方だけの責任として目を向けるのではなく、双方の行動改善に目を向けていくことが重要です。そのうえで、世代の特徴や価値観を理解し、それぞれの立場を尊重した対話や関わりが求められます。また、組織のそもそものあり方も考えていく必要もあると考えます。
人材の流動化が加速している現在において、人材の確保・活用は組織における最重要課題の一つです。安定的かつ革新的な組織をつくっていくためにも、本コラムの内容が参考になれば幸いです。
LEADCREATE NEWS LETTER
人事・人材開発部門の皆さまに、リーダー育成や組織開発に関するセミナー開催情報や事例など、実務のお役に立てるような情報を定期的にお届けします