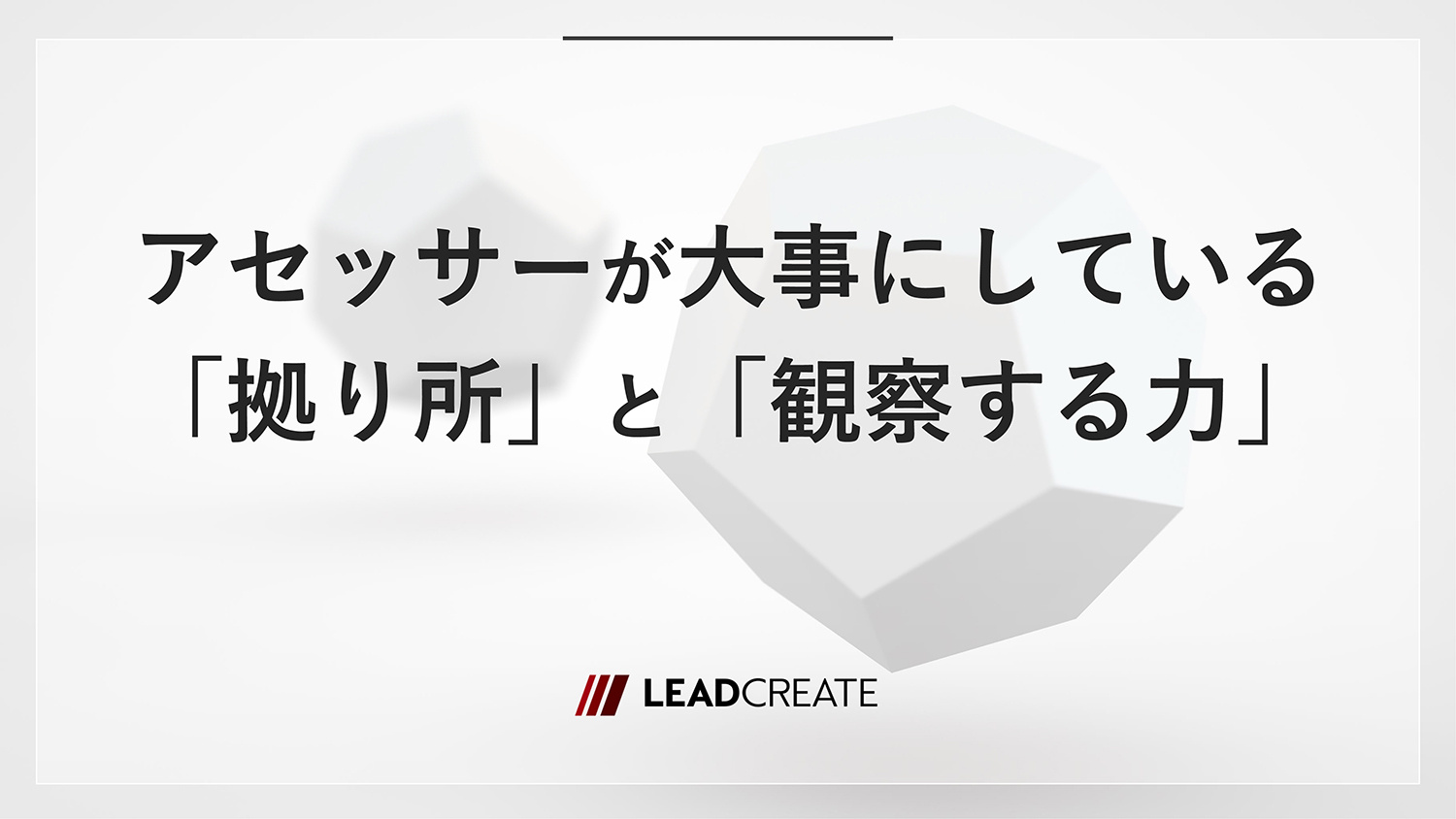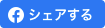ビジネス環境が劇的に変化するなか、社員に求める知識・スキルの見直しが迫られている企業も多いと思われます。
一方、社員が自身のキャリアを見つめ直し、能動的に学習する機会は少ないと言わざるをえません。組織を永続的に発展させる上で、どのような取り組みを導入するにせよ、各々が自身の能力を内省的に理解すること、さらに組織全体では、研修で得られた気づきを現場での実践に活用し、成果として残せるよう支援すること、が重要であると考えます。
本コラムでは、組織の戦略の実現や課題解決のため、アセッサーがどのような支援を行っているかをまとめました。
この記事の著者

株式会社リードクリエイト
プリンシパルコンサルタント
宮崎 圭介
2015年よりリードクリエイトに参画。 受講者との間に極力境界線を設けず、職場で有効な実践知を伝える。現場で成果を上げるため、一緒に考える姿勢で関わることにこだわる。クライアントの特徴にあわせて、双方向の対話を重視したプログラムを展開中。
アセスメントプログラムの特徴とアセッサーの関わり方
昨今、タレントマネジメントやサクセッションプランの導入に向けて、さまざまな企業からの問い合わせが増えています。人の成長を通じて組織が持続的に発展していく上で、リーダーの育成と適材適所の登用は欠かせません。組織の未来を託す人材を発掘し、その能力を最大限に引き出すための指針が必要とされています。
アセッサー(訓練された評価者)は、研修形式のプログラムの中で、人の適性や知識、行動や能力の特徴を分析します。リーダーシップの発揮が求められるさまざまな場面を設定し、どのような状況下で、実際どのような行動をとっているか、事細かに観察・記録します。そして、その背景にどんな職責を果たそうとしたか、どのような結果をもたらしたかについて、分類・評価することに特化している点が、アセスメントプログラムの特徴です。受講者にとって最適なシミュレーション環境を提供し、そこで発揮された行動事実から、受講者の能力の保有度合いを測定します。
組織のリーダーに求められる役割は、事業上の要所の問題や課題への手立てを講じ、価値創出への道筋を描く「事業推進」と、個とチームの潜在能力を引き上げ相乗効果を生み出す「組織活性」に分かれます。弊社のアセスメントデータ分析によると、これまで弊社のプログラムを受講したリーダー人材のプロフィールは、組織内外の人材と良好な人間関係を築いて(主に組織活性を軸に)安定的な成果を目指している傾向が見られました。一方で、中長期的な視点で組織や変革に向かう行動は少なく、周囲への過度な遠慮が新たな価値創出を妨げている(事業推進にブレーキがかかりやすい)実態も窺えました。
※参考情報:人材アセスメント分析レポート2024-1万人のデータから見えるリーダー人材の実態
このような分析結果を導き出すまで、アセッサーは受講者の志向性や価値観に迫る働きかけを駆使しています。人間は誰しも、何らかの核となる信念を持ちつつ、さまざまな刺激を吸収し、進化し続けようとする生き物と考えられます。アセスメントプログラムの現場において、アセッサーが何を拠り所に行動事実を観察し、どのように受講者に向き合っているか、より詳しく具体的に見ていきます。
客観性
少し離れた立ち位置から個人の能力を俯瞰的に捉える
殆どのビジネスパーソンは、自分自身の「能力(強み・弱み)」を正確に把握しているようで、本質的には理解し切れていない現象が見られます。人はそもそも、自分自身を客観的に評価することが難しい、と考えられています。心理学には「ポジティブ・イリュージョン」という言葉があります。誰であるにせよ、人には「自己を過大評価し、肯定的に知覚する」認知バイアスが働きやすい傾向が見られます。ある研究では、リーダーシップ能力について70%の人が自分は平均より上と認識しており、平均よりより下とみなす人は僅か2%しかいなかったそうです(参考文献: 榎本博明著「ビジネス心理学大全」日経BP日本経済新聞出版本部、2020年)。
また、長い期間に渡って同じ職場で、同じような職務について学び続けた結果、前例踏襲の仕事の仕方や過剰適応の状態に陥っている事例が多く見られます。「業務が属人化している」「仕事の個別最適化が進み、全体像が見えない」といった職場環境が、自身の能力を客観的に捉えられない思考を増幅させているようにも映ります。
アセッサーは、多面的かつ多角的に個人の能力をメタ認知することに、多大な時間と労力をかけています。仕事の現場を離れて、組織の外で仕事に関わる内容を学ぶ機会を最大限に生かせるよう、行動事実の分析・解釈にアセッサー全員で関わります。コースの責任者であるリードアセッサーと、グループ担当のアセッサーによる「複数体制による複眼評価」「複数の演習機会」を通じて、客観的な評価の信頼性を担保しています。
また、最近の傾向として、研修前に事前の説明会を実施したり、研修終了後のフィードバックを行う機会に上司やステークホルダーが参加するプログラムが増えています。前後の場にアセッサーも参画することで、研修で学んだことの俯瞰的な把握につながり、得られた気づきが実務に反映されて、組織課題の解決へと広がるよう働きかけます。アセスメントプログラムを実施するだけで終わらせず、参加者が所属している上司や同僚の理解と協力を得るといった、周囲からの関わりも重要です。
探究心
なぜその行動・結果に至ったか、個々人の動機を価値観まで掘り下げて考える
自身の能力を客観視できたとしても、「働き方改革」「人的資本経営」といった社会・経営課題を解決することとの間には、まだ大きなギャップが存在します。個々に必要とされている能力開発は、高度化・複雑化していく一方です。単一の原理原則で課題の全体像を捉えて、解決策を見出すことは難しいと言わざるをえません。
弊社のアセスメントデータ分析では、事業推進の思考領域を中心に、個人が持つ保有能力のバラつきが進んでいる、といった解析結果を示しました。問題を解決できる能力を持つ社員と持ててない社員の乖離が広がっている、といったお悩みを聞くことが多々あります。個々の特性を全く考慮せず、共通の対策を立てることには注意が必要です。各社の現状を踏まえて、現実的で効果的な解決策を設計する丁寧なプロセスが不可欠です。
※参考情報:人材アセスメント分析レポート2024-1万人のデータから見えるリーダー人材の実態
アセッサーは、個人の課題を可視化し、相互にフィードバックする対話時間を設けて、個人のキャリアを自分の意思で描くことを支援します。対話の場づくりにあたって、米国の心理学者であるデビッド・マクレランドによって提唱されたといわれる「氷山モデル」という考え方を紹介します。氷山は、その一部のみが水面上に見えており、その大半は水面下に沈んで見えません。個人の行動を、コンテント(制度・仕事の内容といった目に見えやすいもの)とプロセス(関係性・感情といった目に見えにくいもの)に切り分け、両面から理解することが必要です。加えて、表出する行動にはその人の信念や世界観が反映されています。認識した事実に対してどのような解釈をするか、受講者本人から意図や目的を導き出すことを重視しています。仕事をしていく上で目に見えにくいもの(個人の動機や価値観など)まで掘り下げて、グループダイナミクスの相互作用を活かしつつ、個人の動機や価値観に根差している課題の本質と向き合えるように働きかけます。
実際の研修現場では「直前に記録した演習場面の動画」と「即時フィードバック」を活用します。体験した直後の動画視聴は、行動変容に大きな影響力をもたらします。研修後のアンケートでも、演習後に映像を見る時間が最も強烈な印象として残った、という回答が多数寄せられています。アセッサーは、厳しい現実に向き合えるようグループの心理的安全性を担保し、受講者同士で相互フィードバックを行う流れをファシリテートします。特にネガティブなフィードバックは「鮮度」が命です。本人の成長を願いつつ、耳障りの悪いことも率直に意見交換できる場づくりに配慮します。言葉遣いに細心の注意を払い、率直なフィードバックを受け止め合う対話環境の構築に腐心します。
柔軟性
多面性を持つ行動原理をさまざまな見方から分析し最適解を探る
自身の能力を客観的に理解し、根源的な動機や価値観に気づいたとしても、行動変容が起きなければ、組織の戦略の実現や目標達成に向けた課題が解決に近づいた、とは言えません。プログラムの最後に予定されることが多いフィードバック面談でも「で、私は何をすればよいでしょうか…」と質問を受ける状況も頻繁に発生します。
各々が抱える課題は、個別具体的です。個人が抱える理想と現実の状態はさまざまで、現状と理想のギャップを明らかにする必要があります。現状と理想のギャップ(問題)を生んでいる要因(課題)を明らかにした上で、解決策を自己選択することを促します。
アセッサーは、演習で観察された事実と、共通言語として定義されている基準を踏まえて研修参加者と話し合い、各々の現場に適合した最適解を見出すことを支援しています。各々が抱える課題を網羅的に取り上げ、本人の意思・能力と会社から与えられているミッションを踏まえて、最も効果性が高い解決策を考えます。お互い捉えている事実と、会社から求められている基準をすりあわせて、相手の立場に立った言葉に翻訳して伝えることを心掛けています。
ここで最も大事なことは、アセッサーと研修参加者に一定の信頼関係が醸成されていることです。フィードバックは「何を」言われるかよりも「誰に」言われるかが大事、と言われています。突き詰めると、人間は往々にして感情に支配されています。全く同じ行動事実について、価値観が合わない相手から言われるとカチンとくる一方、信頼する相手からの言葉であれば心に響く、といった不都合な心の動きは避けられません。相手の成長を願う気持ちを胸に抱いて、その人の持ち味を尊重しつつ、心理的な動きをしなやかに吸収する柔軟さを持ち合わせることが鍵になります。一方通行で決めつけ的なフィードバックにならないように細心の注意を払うことを肝に銘じています。
人と組織の成長課題を絞り込む「観察する力」
アセスメントプログラムでは「人は同じ状況下では、同じような行動を選択する可能性が高い」という行動科学の考え方をベースに、意図的な刺激を持ったシミュレーション環境を設定し、各演習での行動事実を網羅的に観察します。ただ漫然と観察するだけでは、表出行動の違いや差を捉えることができません。各演習を客観的かつ俯瞰的に理解し、受講者本人が固有に持つ本質的な動機を掘り下げます。
逆説的ではありますが、人は「普段の会社環境とは異なる状況下で、異なる行動を選択する」時に、その人ならでは特徴が現れます。安定的な世の中であれば、アセスメントプログラムで用意するような特殊な環境は必要としないのかもしれません。ただし、VUCAという言葉に代表されるように、これからの世の中は多様性が広がりこそすれ、狭くなる可能性は少ないと考えられます。これまでと異なる環境におかれても、その人らしさや組織の特徴を生かして成長し続けることが必要とされています。
突き詰めて考えると、アセッサーとして最も必要な素養は「人と組織の特徴を、より広く深く柔軟に観察する」ことです。人間は多面体だと言われており、他人と異なる側面を無数に持っています。一方で、刺激が少ない環境・変わらない関係性の中にいる人ほど、固着化した行動原理を持ってしまいがちです。本来の持ち味を発揮したり、成長の可能性を追究したりすることができていない側面も多く見られます。アセッサーは、その人の成長の核となる動機を掴んで、固有に持つ潜在的な能力を特定し、あるべきリーダー像などと比べて、本人の成長課題を具体化します。そのために何よりも必要な力は、客観的な立ち位置から健全な探求心と柔軟性を維持しつつ観察する力です。
まとめ
- アセッサーは、受講者の行動事実から能力を測定している
- 能力を測定する際の拠り所として、以下のプロセスを大切にしている
・少し離れた立ち位置から個人の能力を俯瞰的に捉える(客観性)
・行動や結果に至った動機を価値観まで掘り下げて考える(探求心)
・多面性を持つ行動原理をさまざまな見方から分析し最適解を探る(柔軟性) - いずれのプロセスも成長課題を絞り込む「観察力」が鍵となる
いかがだったでしょうか? 今回は、アセッサー(訓練された評価者)が、何を拠り所に人と組織の特徴を掴もうとしているかに焦点を当てて解説しました。
この記事を読んだ方が、少しでもアセスメントプログラムのプロセスについて理解を深める機会になれば幸いです。
LEADCREATE NEWS LETTER
人事・人材開発部門の皆さまに、リーダー育成や組織開発に関するセミナー開催情報や事例など、実務のお役に立てるような情報を定期的にお届けします