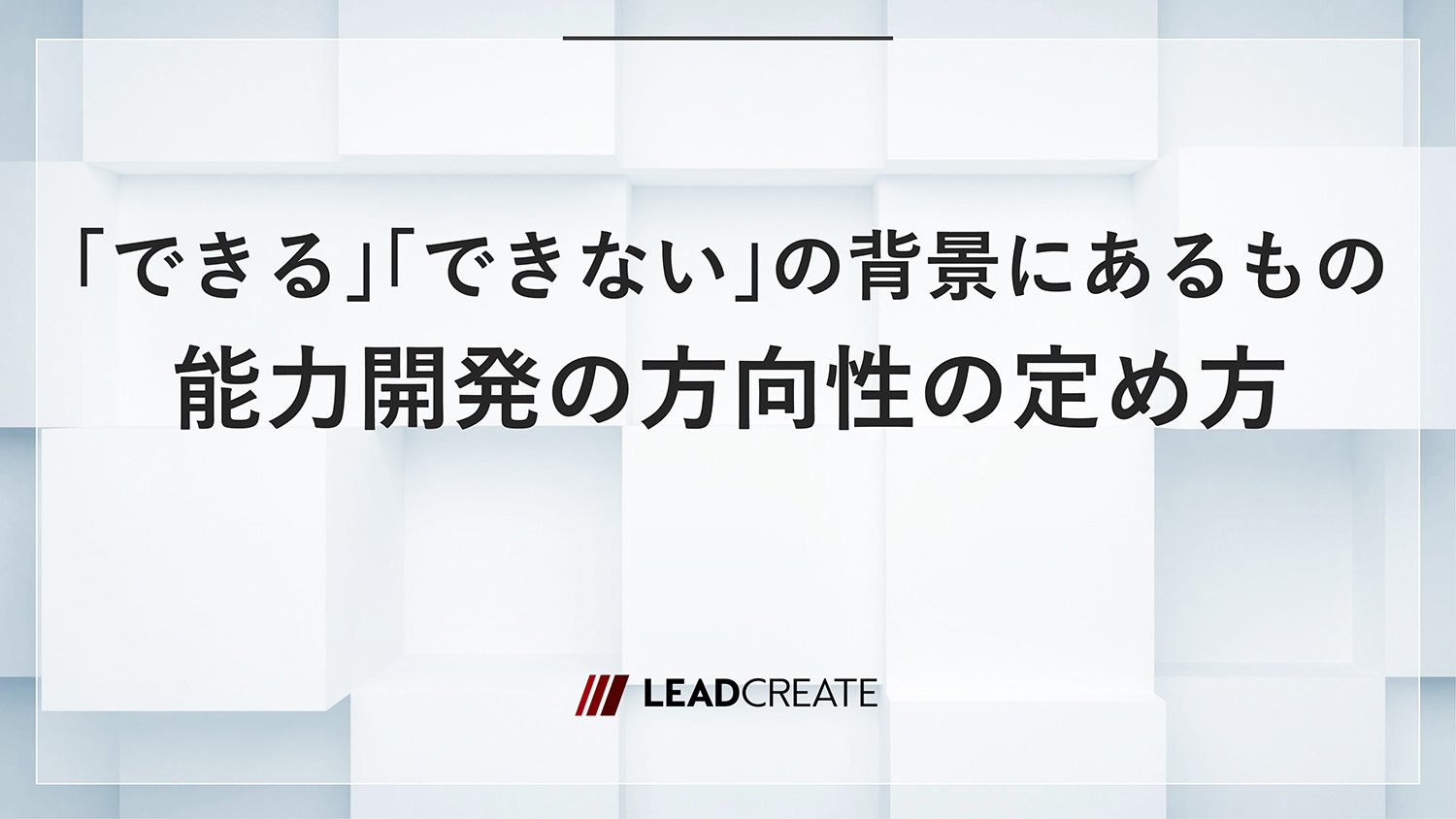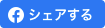本コラムでは、企業の人事担当者、特に育成担当者が一度は感じるであろうジレンマ「育成施策を充実させているのに社員が成長しないのはなぜか?」について考察します。
アセスメントプログラムの受講者一人ひとりと真摯に向き合いながら、私たちアセッサーが「日々感じている視点」を共有するとともに、個々の背景を踏まえて「能力開発の方向性をどのように定めていくか」についての考え方をご紹介します。
この記事の著者

株式会社リードクリエイト
チーフコンサルタント
殿村 幸彦
生命保険業界における人材育成部門での業務経験を経て、2022年5月よりリードクリエイトに参画。コンサルタントとしてアセスメントプログラムや研修に登壇。参加者相互の交流を促し、「研修で得られた気づき」を言語化することを通じて、「職場で活用できる」研修を実施。
「○○ができる」のはなぜか?「○○ができない」のなぜか?
ある人の特徴を挙げるとき、「あの人は魅力的なプレゼンするよね」「でも、細かい部分は苦手で、感覚で仕事をしている感じがするよね」というような会話が交わされることがあります。
これらは、ある人に対する「○○ができる・○○ができない」を話題にしたものですが、もし、あなたがこの人物の能力開発に関わる立場だった場合、この人物の意識や能力面に対し、どのような対策を考えるでしょうか。
- 対策 - 根拠をもとに細かいことも考えてもらおう。問題解決研修を実施しよう
これはいわゆるコインの裏返しと言われるもので、シェアが落ちている(問題)→シェアを上げろ(対策)といっているのと構造は同じです。問題解決研修がフィットすることもあるかもしれませんが、そもそも研修に興味を持ってもらえない、研修に参加しても効果がでない、といったことのほうが多いかも知れません。一方、「できる」のはなぜか?「できない」のはなぜか?を突き詰めて考えれば、個々の克服すべき課題が見つかり、育成施策も的を得たものが打ちやすくなるのではないでしょうか?
それでは、会議や打ち合わせの場面を例に、「できる・できない」の背景を探求していきます。会議や打ち合わせをしていると、特に役割を指定していなくても、参加者それぞれの役割が自然と分かれていくことがあります。具体的には、会議を進行する人、アイデアを出す人、盛り上げる人、意見を受け止める人、意見を浸透させようとする人、などが挙げられます。また、役割という言葉はフィットしませんが、評論家、傍観者、流れに乗るだけ、といった傾向を示す人もいます。
では、なぜ人々は異なる役割や傾向に分かれるのでしょうか。その背景を、発揮行動→能力特性→個人特性という流れに沿って探求します。発揮行動とはまさしく、目に見える行動のことです。例えば、ある人が会議を進行し始めると、周りの人もその行動を認識します。会議を進行する人を「できる・できない」で整理すると、その人は会議を進行することは「できる」一方、自らの意見を浸透させることについては、苦手または意識が向かないなどの理由から「できない」といった場合があります。先述のとおり、「あの人はこんな人だね」で留まるのではなく、「できる・できない」の背景を探り、個々の克服すべき課題を見つけることが肝要です。背景を探るため、発揮行動に影響を与える、能力特性と個人特性を見ていきます。
背景① 能力特性
能力特性は、その人の「能力の傾向」です。分かりやすく理解するため、能力として「できる・できない」と捉えてください。人は自分が「できる=得意」と感じる能力を活かそうとします。一方で、「できない=苦手」と感じる能力を発揮することには消極的になります。
先ほどの会議を進行する人のケースで、「できる・できない」についての具体例を挙げます。
「できる」と感じる能力
・コミュニケーション力…周囲に話題を提供し、相手の意見に耳を傾ける力
・チームワーク…他者と協力して目標を達成する力
・柔軟性…状況に合わせ柔軟に対応する力
・問題解決力…問題解決プロセスの流れを踏まえて討議を進行する力
これらの「できる」と感じる能力を総動員し、会議の進行役として活躍します(「できる=得意」と感じる能力を活かそうする)。
「できない」と感じる能力
・リーダーシップ…チームやプロジェクトを先導する力
・自己主張…自分の意見を明確に表現する力
・意思決定…皆が躊躇する場面でも果断に決断する力
・批判的思考…与えられた情報や周囲の意見に対して疑問を持ち、真偽を確認する力
会議の進行役として、合意形成への貢献は大きいものの、集団内での発言は論点提示や他者の発言を促すなどの問いかけが中心となり、一度も自身の見解を発言しないといったことが見られます(「できない=苦手」と感じる能力を発揮することには消極的になる)。
背景② 個人特性
次に個人特性について見ていきましょう。個人特性とは、その人の「考え方や行動の傾向」です。その人特有の気質、意識や関心の向かう先、行動のクセといったほうがイメージしやすいと思います。先ほどの会議を進行する人のケースで個人特性を探ってみます。
例えば、参加者全員が納得できる合意を目指すという個人特性を持っている場合、これはどのようにして形成されたのでしょうか?それを紐解くには、メタ認知(認知していることを認知する)により、自分の考え方や行動を客観的に見る必要があります。メタ認知を実践するために、「認知の4点セット」というフレームワークを用います(参考文献: 熊平美香著「リフレクション(REFLECTION) 自分とチームの成長を加速させる内省の技術」ディスカヴァー・トゥエンティワン、2021年)。このフレームワークは、意見は過去の経験、感情、価値観から形成されているという考え方に基づき、意見、経験、感情、価値観の4つの観点で探求を深めます。
参加者全員が納得できる合意を目指すという個人特性を持つ人が、集団での合意形成はどうあるべきか?と問われれば次のような意見を述べるでしょう。
経験:学生時代の部活動で部長を務めていた。強いリーダーになろうと自分の考えで部の方針を決定し、運営していたが、一部の部員から部長のやり方に納得できないと反発を受けた。
感情:全員が納得しない形で部を運営することに強いストレスを感じた。また、部員に対しても申し訳ないと思った。
価値観:チームワークが大切なので個人の意見よりもチームの調和や協力を優先したい。また公正なプロセスを経て意見が尊重される環境が大切だ。
一例を紹介しましたが、誰にでも今の自分につながる印象に残る経験や節目となる経験があります。何もないところから、メンバー全員が納得できる合意を目指すという個人特性が現われるわけではなく、経験、感情、価値観という背景がその人の個人特性を作り上げています。
「できる」の背景の話に戻ると、メンバー全員が納得できる合意を目指すという個人特性があるからこそ、会議では全員の合意を得ることや納得感を高めることに注力します。そのために必要なスキルとしてファシリテーションを学習することで、会議進行が「できる」というように繋がっていきます。
逆に「できない」の背景としては、自身の意見や判断でメンバーを先導するという個人特性を持たないため、そのような意識も働かず、そのためのスキルも磨こうとしないから「できない」となります。
このことから、個人特性はその人特有の気質、意識・関心の向かう先という意味合いのみならず、能力の源泉とも言えます。
【例】「あの人は柔軟さに欠ける」の背景を紐解く
能力特性や個人特性から「できる・できない」の背景を探るイメージを掴んでいただくために、もう一例ご紹介します。あの人は柔軟さに欠ける、という人の背景には何があるのでしょうか?例示として、一対一の対話場面で、相手の発言や態度に応じた対応ができず、一本調子の対応を取るなどで柔軟さに欠ける場合の背景を紐解いてみます。
思考面の問題
相手の言っていること、どんな気持ちを抱いているかも分かるが、それに対して、自分がどう反応すべきか整理ができない、何か対応したくても手札が見つからないといった場合は、思考面の問題が考えられます。適切な対応ができない背景には、何らかの思考スキルが身についていないという状態であるため、能力特性に分類される問題と言えます。
対人面の問題
相手が、自分から意見を述べることを抑制しがちというコミュニケーションスタイルであるにも関わらず、相手に何度も意見を求めてしまう場合は、対人面の問題が考えられます。他者のコミュニケーションスタイルに応じた対応力が身についていないため、こちらも能力特性に分類される問題と言えます。
価値観の問題
自身は、チームの調和や一致を大切にしているという価値観を持っているが、相手は、強い個人が集まってこそのチームであり、そのためには多少の衝突は仕方がないという価値観を持っている。その結果、いくら話し合っても相手の考えを受け入れられず、話が平行線を辿る場合は価値観の問題が考えられます。互いの気質の違いであるため、個人特性に分類される問題と言えます。
能力開発の方向性
ここまで、「できる・できない」の背景を探求してきましたが、個々の能力開発の方向性を定めるには目に見える発揮行動だけではなく、その背景にある能力特性や個人特性にも着目する必要があります。単純に、発揮行動として「できない」ことを「できる」ようにしようとするだけでは、有効な対策にはなり得ません。例えば、先ほどの個人特性が異なる人に対して、とにかく相手の話に肯定的な反応を返しましょう、というノウハウだけを伝えて実践するように促しても、価値観の問題でどうしても柔軟になれないという人には苦痛になるだけです。
これらの事例が示すように、全員一律に「できない」ことを「できる」ようにするためのプログラムを展開するという発想では、個々の本質的な成長課題を見つけて能力開発の方向性を発見することはできないのです。
個々が「できる・できない」の背景には何があるのか、自身の背景を振り返ることで、どの能力を開発すべきかが見え、価値観の問題が生じていることにも気づくことができます。
価値観はその人そのものであるため、容易に変えられるものではありませんが、価値観によってこの分野で活躍してみたいという、自身の能力開発の方向性を認識することができます。また、副次的な効果として、自身の価値観を見つめる過程で、自分には過去の経験からつながる大切な価値観がある、他の人も大切な価値観があるはずだ、と感じることで、他者の価値観に対する寛容性が芽生えることも期待できます。
まとめ
その人の表面上の行動(発揮行動)ではなく、その背景(能力特性・個人特性)にアプローチすることで、その人の能力開発の方向性が見出されます。
個々人が能力開発の方向性を認識すれば、自身の成長に繋がると感じられる育成施策に積極的に参加するという流れも生まれ、少なくとも育成施策に参加することでモチベーションが下がるということはなく、成長に繋がる可能性は高まります。
まずは、育成施策の中に振り返りセッションや個別面談の時間を取り入れるなど、個々が自身の背景を振り返る時間を設けてみてはいかがでしょうか。
LEADCREATE NEWS LETTER
人事・人材開発部門の皆さまに、リーダー育成や組織開発に関するセミナー開催情報や事例など、実務のお役に立てるような情報を定期的にお届けします