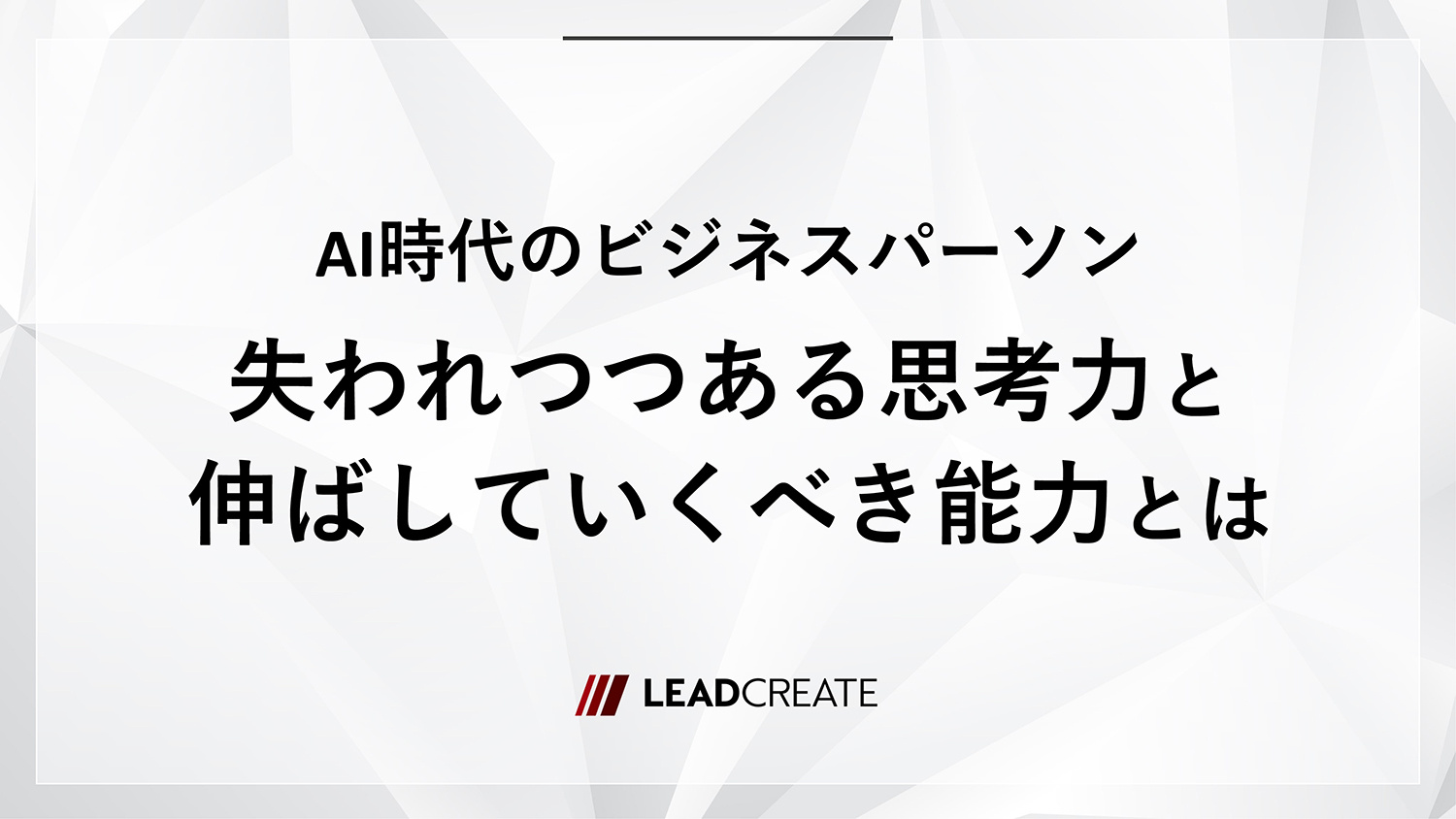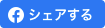生成AIの本格的な社会実装が為される中、人間の「考える力」が急速に劣化しているのではないかという漠然とした問題意識を持っている方は多いのではないでしょうか。今後の社会の方向性として、AIを代表するテクノロジーとの共存は、避けては通れないという前提に立った時、私たち人間は、何に価値を見出し、どのような活動に注力していくべきなのでしょうか。
本コラムでは、ビジネスパーソンやリーダーに求められる「思考する力」に焦点を当て、これからの人材育成について考察してみたいと思います。
この記事の著者

株式会社リードクリエイト 常務取締役 菅 桂次郎
2003年7月よりリードクリエイトに参画。人材マネジメント全般に関わるコンサルティング営業を経て、2014年よりアセスメントサービス全般の開発から品質マネジメントを中心に、リーダー適性を見極めるアセスメントプログラムの進化を目指して活動を展開中。
「思考しなくても良い社会」の到来
皆さんは、1953年に出版された「華氏451度」というSF小説(1966年に映画化)をご存じでしょうか。情報の全てがテレビやラジオによる画像や音声などの極端に一般化・単純化された感覚的なものばかりの社会において、本の所持や読書が禁じられた架空社会における人間模様が描かれた作品です。小説の中の世界では、「思考する」という害悪の根源である「本」の全ては、昇火士(消防士の逆)によって燃やされてしまいます。表面上は穏やかな社会として描かれている背景に、人間の思考力と記憶力が失われ、自分で何も考えなくなった世界の末路がどうなるかというメッセージが込められた内容です。
子どもの頃に観た映画の記憶を頼りに、35年ぶりに改めて小説を読む機会を得ました。当時から社会は大きく変化し、圧倒的な情報化社会になった現在において、華氏451度の世界が近づいていることへの恐怖と危機感を抱いています。極端に単純化されたショートムービー、自分の嗜好に偏った動画コンテンツ、居心地の良いコミュニティ内での簡素化されたメッセージ、これらの閲覧に一日の大半を過ごす日常。その結果、本を読んだり、文字を書いたりする思考時間は極端に削られ、自分で考えるよりも「検索する」「生成AIに聞く」ことで当面の回答を得るための最短距離を模索する。電車の中でもお風呂の中でも、ほとんどの時間をスマホ画面と共に過ごす日々。多少のディティールの違いこそあれ、まさに華氏451度の世界になってしまっているのです。
たしかに世の中は圧倒的に便利になっているのだと思います。洗濯もボタン一つで終了するため、外に干すかどうかの判断や時間も考えなくても問題ありません。極端に単純化された「ボタン」の押し方さえ理解すれば、洗濯もお風呂も調理も買い物も、思考作業から解放されたということです。同じようなことが、ビジネスの至る所にも増えてきており、何も考えなくても業務ができてしまう「異常なほどに便利な世界」に近づいているのが今なのだと思います。
決して、AIなどのテクノロジーを頭ごなしに否定する意図はありませんが、「手放してはならないモノ」があるのではないかという問題提起です。特に思考するという行為は、人間に与えられた特殊な力です。想像の世界では、人は何者にもなることができます。空を飛ぶこともできますし、学生時代に戻ることも可能です。要は、思考には制約がなく、無限に広がる自由な空間だということです。そして何より、言葉そのものを即物的な意味で理解するだけではなく、文脈やメタファーから真意を捉えるという特殊な力を持っているはずです。「月が綺麗ですね」という言葉で、「I love you」を表現する感性を失ってはならないのだと思います。
この20年で失われた思考力の種類
この数年では「AI」がテクノロジーの代表ではありますが、20年のスパンで考えると「インターネット」と「スマートフォン」が外せないキーワードです。また、ビジネスにおいても、2000年代前半にネットワークインフラも整備され、多くの一般社員が使いこなす時代へと進展し、働く環境が激変したと言えるのではないかと思います。紙を軸とするアナログ的な仕事から、メールやSNSツールなどのデジタル的な仕事へと変化し、その過程において、「使う必要がなくなった力」「日々劣化している力」の代表例を6つ挙げてみたいと思います。
①記憶力
まずはなんと言っても「記憶力」です。昔はクライアントの住所や電話番号を覚えていたという私と同世代の方も多いではないでしょうか。検索エンジンに頼ることで、自分で情報を覚えておく必要性は圧倒的に減少しました。知識の暗記よりも、「どこで情報を探すか」が重要視されるようになり、記憶力は相対的に劣化の一途を辿っています。
②論理的思考力
二つ目は「論理的思考力」です。原因と結果、目的と手段など、自分で筋道を立てて思考する力も、AIツールの出現によって急速に失われつつあるように感じています。特に、データ分析や計算的な推論は、複雑な思考プロセスの理解を飛ばして、結果だけを利用することが増えていき、更なる劣化が進むものと考えます。
③批判的思考力
三つ目は「批判的思考力」です。ソーシャルメディアのアルゴリズムに基づくフィルターを通して提示される情報には、個人の志向にあったものが取捨選択され、「自分にとっては心地の良い」偏った情報に依拠しがちです。また、AIによって自動生成されたコンテンツや情報を精査する意識が薄れる可能性が高く、提示された情報を無批判に受け入れてしまうリスクもはらんでいると言えます。
④創造的思考力
四つ目は「創造的思考力」です。少し前までは、AIが最も実現できない領域という論もありましたが、アートやデザインなどの創造的な分野においても、人間以上のパフォーマンスを発揮する可能性が高まっています。絵画や小説、音楽の分野においては、既に実証されており、クリエイティブな領域においても、プロフェッショナルに頼らなくても一定のクオリティが誰でも出せる未来が近づいているように感じています。
⑤直感的思考力
五つ目は「直感的思考力」です。天気や渋滞状況などの判断も、既にAIの判断に依存しているのが実情です。商談時における受注確度(見込みの度合いや可能性)なども同様に、これまでの経験や勘ではなく、エビデンスに基づく高度な予測の方が、人間の直感を上回るようになってきています。
⑥人間関係における感情的理解力
最後は「感情的理解力」です。オンラインツールやSNSツールなどのやり取りが主流となり、対面における深い共感を伴う対話機会は圧倒的に減少しています。また、AIアシスタントやチャットボット、自動音声ガイダンスなどの活用により、人間同士のコミュニケーションが失われることによって、非言語的なシグナルを読み取る力は劣化していっているのではないでしょうか。
私たちビジネスパーソンが今後伸ばしていくべき思考力とは何か
ここまで見てきたように、インターネットやAIを代表するテクノロジーの進化によって、私たち人間の思考力は「敢えて使わなくてもよいモノ」になりつつあります。一方で、自分の将来や組織が向かうべき方向性などの意思決定は、生身の人間が為すべきであると少なくとも私は考えます。そうした時に、テクノロジーに依存することなく、人間固有の思考力として磨き続けていくべき、意識的に伸ばしていくべき力を4つにまとめてみました。
①目的意識
意味や意義を見出す力です。単純な正しさや確率的な確からしさの枠を超えた、理想や志、大義や提供価値から思考する行為は、これからより強く求められるのではないかと考えます。同じ業界、同じような形態を取る会社でも、各社の思想によって向かう方向が違うように、「何のために?」という問いを持つことは、組織を発展に導くうえで全てのビジネスパーソン、その中でも特にリーダーに必須で求められる要件だと考えます。
②状況把握力
事実に基づいて全容を把握する力です。正誤混在の圧倒的な情報量に加え、相互が複雑に絡み合う現状においては、個別事象を客観的に捉えるとともに、全体像を関連づけて捉えることが重要となります。現実社会においては100%の状態を把握することが困難だからこそ、要点を的確に押さえて全容を包括的に押さえていく力は、その後の意思決定における基盤となるはずです。
③論理思考
脈絡を作る力です。ある状態を起点に、仮説や推論を立てながら「ストーリーとして意味づけする力」とも言い換えられます。特に昨今のビジネス環境においては、前例のない、不透明かつ複雑な状況下での判断が求められます。物事の真理や真相に向かう思考は、今後の組織内外で発生する問題解決においては必須の力と言えるでしょう。
④構想力
新たな将来像を描写する力です。「白紙のキャンバスに未来の組織や事業を描く力」とも言い換えられます。既知・既存の枠組みや過去の問題に囚われることなく、未知の世界を具現化する力は、多くのビジネスパーソンが最も不得手とする領域でもあり、この先もより一層求められる力であると考えます。
今後の人材育成に重要なこと
私たちが身を置く現在は、ビジネスを包含する社会全体において、大きな構造変革の中にあると言えます。AIを代表するテクノロジーの更なる進化によって、「仕事の進め方の変化」ではなく「仕事そのものの変化」が訪れようとしていると言えます。本コラムでは、その影響によって生じる人間の思考力にテーマを絞って考察してきましたが、人材育成(特にリーダー育成)の文脈においても、従来のアプローチとは異なる何かを講じる必要性が高まっているのではないでしょうか。
この先の未来を予測することは不可能であるため、何か絶対的な正解を提示できる訳ではないのですが、少なくとも私たちリードクリエイトでは、上述の4つの領域の思考力については、これからの組織のあり方を前提に置いた際、外せないモノであると考えています。
これまで行ってきた階層別教育をはじめとする各種研修プログラムや、昇進昇格時の判定基準においても、改めて「将来のリーダーに求められる思考力とは何か?」を問い直す機会なのだと考えます。
まとめ
- 社会全体が「考えなくてもよい状態」になりつつある
- この20年で急速に失われつつある6つの思考力
- 将来のビジネスパーソンやリーダーが意識的に伸ばしていくべき4つの力
今回は、AIをはじめとするテクノロジーの進化がもたらす「人間の思考力への影響」をテーマに焦点を当てて解説しました。この記事を読んだ方が、少しでも人材育成やリーダー育成の未来に対する何らかの気づきに繋がっていたら幸いです。
リードクリエイトでは、企業や組織の人事部門の方に向けて、リーダーの選抜と育成に関わるソリューションを提供しています。自社のリーダー登用における昇進昇格の仕組みを見直したいと考えている、課長や部長など役職者の適性の違いを整理したいと考えている、将来のリーダー育成を見直したいと考えている、といった問題意識やお悩みを抱えている方は、お問い合わせください。
LEADCREATE NEWS LETTER
人事・人材開発部門の皆さまに、リーダー育成や組織開発に関するセミナー開催情報や事例など、実務のお役に立てるような情報を定期的にお届けします